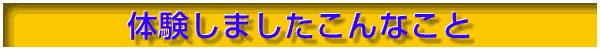
炭焼き 完結編(1/2)
|
一週間後、炭を取り出しにゆく。今回S氏は欠席。K氏とともに車で「夕やけ小やけふれあいの里」へと向かった。山間の小川の川面に朝霧が立ちこめている。寒い朝だ。
受付を済ませ早速現場へ。山の斜面は先週よりも雪の量が増えている。到着すると既に焚き火が焚かれ、もう説明が始まっていた。簡単な説明後、出来上がった炭の取り出しにかかる。先ずは伏せ焼きの穴を掘り返す。土をどけて竹の上に被せてあったトタン板を撤去。ところが出てくるのは灰ばかり。今回はあまり巧くいかなかったようで半分以上が灰となってしまった。それでもいくらかの炭を取り出して一同ホッとする。
しかし灰や細かく砕けた炭、焼けて赤くなって滅菌された土などは畑に撒けば土壌改良に使える。地元で畑をやっている参加者が袋に詰めて持ち帰る。 炭質は伏せ焼きの方は硬く、可搬釜は急加熱するので早く炭化するとのことでこちらは柔らかい。他に缶に入れた細枝を焚き火に入れて作った炭もある。これはマドラーとして使える。小さなものならこのようにして炭が作れるのだ。今回の出来は伏せ焼き30点、可搬釜70点、と銀爺こと杉浦氏が採点する。炭は毎回出来が違うそうで熟練するにはかなりの経験が必要とのことである。
|
|
|
|
Created by Thomas J.Nakamura
(C) Copyright Thomas J.Nakamura 2003. All Rights Reserved.
著作権法により著作権者に無断でこのページの内容の転載等は禁じられています。




